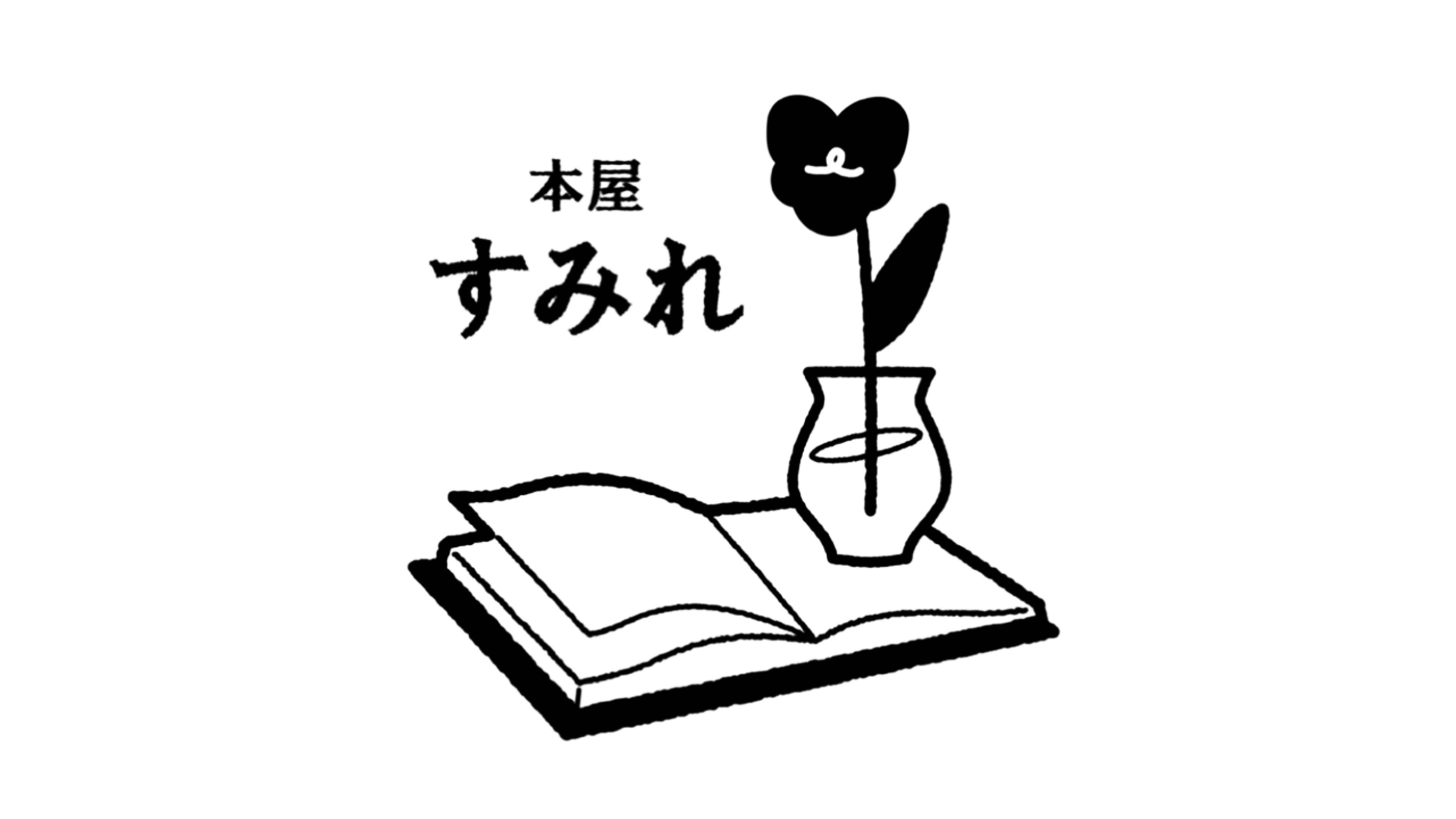-

その日暮らし
¥1,760
坂口恭平 ずっと向き合えずにいた寂しさの正体がわかったことで、僕ははじめて、自分を信頼できるようになった。 コロナ禍にはじめた畑。熊本の土地とたいせつなひとたちとの出会い。うれしさも苦しさも分かち合える家族との昼夜をへて、僕は自分のなかにいた、もうひとりの大事な存在と出会った。日々を綴るエッセイの先に待つ、あらたな境地へといたる生の軌跡。
-

愛と忘却の日々
¥1,760
燃え殻 「ロマンチックなことが少なすぎるんだよ」 中毒者、ますます増殖中。 読者渇望の大人気エッセイ集。
-

過去と生きる哲学
¥2,200
SOLD OUT
シャルル・ぺパン 著 永田千奈 訳 いかに過去と上手に向き合うか。幸せに生きるための方法論
-

今日もぼーっと行ってきます
¥2,200
中島京子 著 直木賞作家による、極上のお散歩エッセイ。 「われわれには、「ぼーっとする時間」が必要だ。というわけで、ぼーっとする小さな旅に出ようではないか、というのが、このエッセイの企画趣旨なのである。」 情報や仕事、雑事に追われる日常生活から離れ、気持ちのいい空間を、ただひたすらぼーっと散歩したい。 野鳥公園に天文台、植物園、水族館、美術館。大山詣りに雨の梅園、時にはフェリーに乗って、あるいは天然の冷蔵庫、石の採掘場へ。 日本地図を作った歴史的人物に思いを馳せたり、ハイキングをしたり。 ささやかなお土産を買い求め、銭湯に入り、居酒屋で一杯。直木賞作家の描く、極上のお散歩エッセイ。 (出版元HPより)
-

海と山のオムレツ
¥2,145
カルミネ・アバーテ 著 関口英子 訳 生唾なしには読めない! 美味しい食を分かち合うことの歓び。
-

遺された者たちへ
¥2,420
マッテオ・B・ビアンキ 著 関口英子 訳 最愛の彼を自死で失った僕が、四半世紀を経て書き上げた悲嘆と再生の記録。
-

あたらしい旅をはじめよう 変わることを、恐れない。
¥1,650
SOLD OUT
松浦弥太郎 いくつになっても、人間としての成長はずっと続きます。 あたらしい挑戦を続ける松浦弥太郎が綴る、45の学びを一挙公開。
-

わたしたちの不完全な人生へ
¥2,035
SOLD OUT
ヴェロニク・オヴァルデ 著 村松潔 訳 誰にだってある。このままではいけないと、ふと運命を変えたくなるときが。 あまりにも不運な男は、ある日、「人生のギヤ」を切り替えようとする。「ボブ」と名乗る娘の思春期に悩み、仕事にも疲れ切ったシングルマザーは、酒に逃げるのをやめることにする。少女時代、親友との友情のために映画出演をやめた女性は、ふとあることに気づく。完璧には程遠い人生を受け止めて生きる愛すべき人々を描く連作短編集。 (出版元HPより)
-

人といることの、すさまじさとすばらしさ
¥2,420
きくちゆみこ
-

歩くはやさで
¥1,540
文・松本 巌 絵・堺 直子 本当は奪われているのかもしれない、と僕は思う。 判型:A5判ハードカバー 頁数:64ページ (出版元HP)
-

偶然の散歩
¥2,200
森田真生 思索、数学、子供との時間、今という瞬間… 偶然の日々の中で一度きりのすぐ近くにある、永遠をつかみたい―― その思いを胸につづられ、あふれでてきた、詩のような言葉たち。 散歩は、子どもたちとの本当の散歩のときもあれば、先人や先達との、時空を超えた思索の散歩のこともあった。二度とない偶然の散歩を、心に刻みつけるように書いた。(まえがきより) (出版元HP)
-

巴里の空の下オムレツのにおいは流れる
¥1,760
著 石井好子 滞在先のパリやいろいろな国で出会った料理、家族やお友達との楽しくあたたかな食卓。すてきなエピソードが、食べることの喜び、心を込めて料理をつくる大切さを教えてくれます。 1963年度(第11回)日本エッセイストクラブ賞を受賞、今なお読み継がれているロングセラーです。
-

ささやかな抵抗として
¥1,650
SOLD OUT
『ささやかな抵抗として』 音無早矢 発行 リトルプレス-uchiumi- 壊されやすさを抱えたまま生きのびるために、読んできたもの、考えてきたこと。 (はじめにより) "傷"も"脆さ"もなかったことにはできない。 これらとともに生きていくことを諦めない。 ささやかな抵抗の先には、小さくも力強い確かな光があるのだろうと感じる。
-

日本のうつくしい野菜
¥1,980
著 : warmerwarmer いま日本に流通する野菜の多くは、海外採種の種から育ったもの。国内で品種改良されずに受け継がれてきた野菜は全体の約1%と貴重で、色や形が個性的だったり、おいしさもひと味違ったり。そんな日本の宝ともいうべき古来種野菜を写真メインでたっぷり紹介。(出版元HPより)
-

北欧雑貨図鑑スウェーデン100
¥1,760
日常のあらゆるところに溶け込み、暮らしを快適にしてくれるデザイン。近年では SDGs先進国としてサステナブルなデザインが注目されているスウェーデン。本誌では名作を生み出したスウェーデン生まれのデザイナーから、100年以上の歴史をもつ老舗ブランド、気鋭の若手デザイナーを起用した新規参入のブランドまで、日本でも人気の高い選りすぐりの100件を編集し、資料 性の高い本として届けます。さらに巻末では、国内の北欧雑貨やインテリアショップ情報をまとめて記載します。 (出版元HPより)
-

小さな住まいでほのぼの手作り日和
¥1,760
著 毛塚千代 『私のカントリー』などの雑誌やハンドメイドイベントなどでたくさんのファンをもつ毛塚千代さん。 団地暮らしも、45年目となりました。韓流推しになったりYouTuberになったりと、精力的に活動の幅を広げています。 毛塚さんの住まいとともに、どうしてそんなに前向きに、そしておおらかに日々を楽しむことができるのか、そのヒントを教えてもらいました。 本書は、インテリアや模様替えに関心がある人にはもちろん、時間に追われていたり、漠然と老後について不安を抱いている方に向けて、 肩肘張らず笑顔で生きることを語っています。 何かと気が滅入ることが多い昨今。毛塚さんのように明るくしなやかに生きることができれば、人生はもっと楽しくなる!(出版元HPより)
-

彼女たちに守られてきた
¥1,980
松田青子 著 大好きだった児童文学やドーナツの思い出、“タメ口おじさん”や古くさいマニュアルへの違和感。私たちを勇気づけるエッセイ集。(出版元HPより)
-

禅COJI コジコジと禅のことば
¥1,540
さくらももこ 著 コジコジの1コマ漫画と真理を突く哲学的な言葉×心を整える禅の言葉
-

白い火、ともして
¥1,320
SOLD OUT
西尾勝彦 本作『白い火、ともして』は、芸術方面に進もうとする若い人たちに「創作基礎」の話をする機会があって、その講座の内容を随筆詩の形をとってまとめたものです。 創作に携わって生きている人、生きようとしている人、またその家族や友人の方へ。また、自分らしく創造的に生きるすべての人へ贈ります。
-

ふつうのオオカミたち
¥4,290
セス・キャントナー 著 池澤 綾羽 訳 アラスカ生まれの白人の男の子の、狩猟生活と都会の間で引き裂かれる葛藤を、変容するエスキモー社会とともに描く傑作長篇。ジャック・ロンドンや星野道夫の系譜に連なるネイチャーフィクション。(出版元HPより)
-

静夫さんと僕
¥1,430
原作 塙宣之 作画 ちゃず 話題のエッセイ、待望のコミカライズ! 一緒に暮らすって、面倒くさい。でもひとりで笑うよりはずっといい。 義理の父とのちょっとおかしな二世帯暮らしをコミックエッセイ化! (出版元HPより)
-

本屋の人生
¥1,870
伊野尾宏之 昭和三十二年開店、 令和八年閉店。 材木屋をたたみとりあえず本屋を開いた父。 フリーターからとりあえず本屋を継いだ息子。 伊野尾書店は、ただそこにあるだけの店だった。 (出版元HPより)
-

あしたの風景を探しに
¥3,300
馬場 正尊 建築設計を軸にリノベーションやまちづくり、 公共空間の再生を牽引してきた建築家・馬場正尊によるアイデアを生む論考集。 どんな風景のなかに 生きていたいのか
-

聞くこと、話すこと。
¥1,870
尹 雄大 著 「論理的に話そう」を突き詰めた結果、私たちのコミュニケーションはただの情報のやりとりに陥ってしまったのではないだろうか。